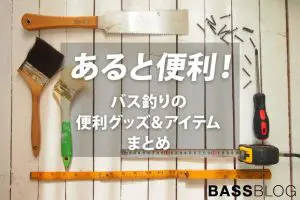今回は、「ブラックバス季節の釣り方」と題して、バス釣り季節別の攻略法についてまとめてみました。
「ブラックバスの季節のパターン(シーズナルパターン)」は、バスの生態についての知識の中で最も重要となる事項で、バス釣りをする上で欠かせない知識です。
ブラックバスの行動を一年の季節の流れで把握することで、バスがその時どのような状況にあるのかを予測しやすくなります。
春なら春の釣り方、夏なら夏の釣り方というように、細切れに季節の釣り方を雑誌やウェブ等で見聞きしてきた方も多いと思いますが、細切れだと付け焼刃的な知識になってしまい、本質的な理解にはなかなか結びつきません。
そこで、ブラックバスの一年の季節の流れを通して見てみることで、これまでバラバラだった知識が、一本につながり、本質的な理解に結びついてきます。
タップできる目次
ブラックバスの季節のパターン(シーズナルパターン)
ブラックバスの春のパターン
バスの春のパターンには、スポーニング(産卵)が絡んできます。
そのため、3つに分けて考えると理解しやすいです。
- 産卵前のプリスポーニング
- 産卵期のスポーニング
- 産卵後のアフタースポーニング
プリスポーニング(産卵前)のパターン
冬が終わり、春になると、冬のあいだ水温の安定するディープに集まっていたバスは、スポーニングのためシャローに移動を始めます。
ディープを出るタイミングは諸説ありますが、そのフィールドの最低水温から7℃水温が上がったあたりからと言われています。
または、日照時間の長さとも言われており、水温が低くても大きなバスはシャローに上がってくる場合もあります。
いずれにしても、この時期は水温がバスの行動と結びつきやすいので、水温をこまめに計測していることがバスの行動を把握する上で大切です。
なぜバスがシャローに移動するかというと、スポーニングのネスト(産卵床)をつくるのが、だいたい水深2m以浅のシャローになるからです。
バスは変温動物のため、自分の体温で卵を温めることが出来ないので、太陽光の熱に頼ることになります。
そこで、太陽光を吸収しやすい日当たりの良いシャローにネストをつくります。
プリスポーニングのバスは、シャローに上がり切る前に、まずディープとシャローの間にある障害物に付くことが多いです。
もし、そのフィールドでバスがよくネストを作るエリアを知っていれば、そこを起点に近くのカバーを狙っていくのが良いです。
スポーニング(産卵)のパターン
プリスポーニングの時期から水温が2℃ほど上がると、先にオスのバスがシャローへ移動を開始し、ネストを作り始めると言われています。
さらに水温が1〜2℃程度上昇すると、メスのバスがシャローに上がり始め、オスのバスが作ったネストを見て回るようになり、メスのバスは気に入ったネストを見つけると、そこでスポーニングを行うと言われています。
しかし、すべてのバスがこのような行動を取るわけではなく、メスが先に上がってきたり、ペアリングしたオスとメスが同時にシャローに上がって来ることも多々あります。
特に、近年のハイプレッシャー化された日本のフィールドでは、バスはこれまでのパターン通りに動くことは少なくなっているようです。
卵の孵化まで
スポーニング期のオスのバスは、ネスト(産卵床)で卵から孵った稚魚が独立する大きさになるまで子育てをします。
卵が孵化する期間は、水温が高いほうが早く、18℃以上あれば4日程度で孵化しますが、14℃程度だと孵化するまでに10日程度かかります。
バスにとっては、ネストで卵を守る期間が短いほうが安全です。
そのため、バスは少しでも早く卵の孵る温かいシャローを好んでネストをつくります。
稚魚の独立まで
オスのバスが卵の孵化から稚魚を守り続けるのは、だいたい1ヶ月程度と言われています。
バスはこの時期、卵や稚魚を狙う外敵に対して攻撃して追い払うようになりますが、このとき攻撃する外敵を捕食はしません。
その理由は、この時期のバスはホルモンの分泌で空腹を感じないためだと言われています。
なので、この期間のバスに対しては食わせの釣りはあまり効かず、他の方法を考える必要があります。
あえて「別の方法」と濁したのは、バスのネストを狙った釣りは、バスへのダメージがあまりにも大きいのでオススメできないからです。
ネストのバスを釣った場合、疲労困憊状態の親バスは命に関わるダメージを負い、放棄されたネストの卵や稚魚は、ブルーギルやコイなどに根こそぎ食われてしまいます。
結果的に、そのフィールドのバスを減らすことでバスが釣れなくなり、釣りもますます難しくなっていきます。
ネストのバスを見つけても、未来のバスを残すために、釣ろうとはせずに温かく見守ってあげてください。
アフタースポーニング(産卵後)のパターン
スポーニングが終わると、メスのバスはネスト付近に数日間は留まりますが、その後少しディープよりのエリアに落ち、サスペンドして体力の回復を待つようになります。
一方、オスのバスはネストの卵が孵化し、稚魚が十分な大きさに成長するまで稚魚を外敵から守り続けることになります。
▼春のバス釣りの詳しい攻略法はこちら
▼アフタースポーンに当たる初夏のバス釣り攻略法はこちら
ブラックバスの夏のパターン
そのフィールドが最高水温に達する時期の前後3〜4ヶ月が、バスにとってのサマーシーズンです。
活性が高くなるバスにとっての適水温は、22℃〜27℃と言われていますが、夏の暑い日に水温が27℃を超えてくると、バスは蒸し風呂のような高温地帯を避け、涼しい場所を求めてディープに移動したり、水温の低いインレットや流入河川に入って行ったり、物陰に潜んで暑さを凌ぐようになります。
このような場合は、高水温のエリアにいるバスは活性が下がるため釣りにくいですが、暑さを凌げる低水温域にいるバスを見つけられれば釣りやすくなります。
また、この時期は水温が下がる朝夕マズメはバスの活性が非常に上がり、シャローで活発にフィーディングをおこないます。
夜釣りでもとても釣れるようになる時期です。
ただし、朝マズメ、夕マズメはシャローに出てくるバスも、日が昇る時間帯はカバーやディープに移動してしまうので、同じシャローを攻めてもまったく釣れなくなってしまいます。
シャローが沈黙してしまったら、日中の釣り=カバーやディープの釣りに切り替えると良いです。
よく釣りに行くフィールドなら、シャローでバスが釣れ始める時間を記録しておくと役立ちます。
その時間が朝夕マズメの釣りと、日中の釣りとの切り替えのタイミングになります。
特に切り替わったばかりの時間は、腹をすかせたフレッシュなバスが入ってきたばかりなので、警戒心が比較的低く、デカバスが釣れやすいです。
このタイミングをつかめれば釣果がグンと上がります。
ブラックバスの秋のパターン
サマーシーズンが終わると、秋のシーズンに入ります。
秋のパターンは、年によって若干の変動はあるが、目安としてだいたい11月半ばくらいまで続きます。
夏の日中に水温が高くて深部でじっとしていたバスも、秋になると涼しくなり、動きまわるようになります。
秋はバスが冬に備えて荒食いに入るため、活性が高く釣りやすいですが、居場所をつかむのが難しくもなります。
特定のストラクチャーにつくのではなく、ベイトにつられて広範囲に散ってしまうからです。
なので秋の釣りの鉄則は、一箇所で粘る釣りではなく、広範囲を探る釣りをすることとなります。
秋のターンオーバー
また、秋には特有のターンオーバーという現象があります。
ターンオーバーは、秋の気候の急激な冷え込みによって起こる。早朝に水面が冷やされたとき、水温の低い水は比重が重いため、冷やされた水が一気に底へ沈みます。
すると、底に溜まっていた低酸素の悪い水が水面へ押し出されます。
これにより、湖底に溜まっていた悪い水が撹拌され、エリア全体が低酸素状態になってしまうのです。
人間が低酸素状態になれば体調が悪くなるのと同じように、バスの活性も下がってしまいます。
このような状況では、酸欠状態のバスばかりとなり、釣り自体がかなり難しいものとなってしまうので、流れ込みなどターンオーバーの起きにくいエリアで釣りをするなどの対策が必要です。
▼秋のバス釣りの詳しい攻略法はこちら
ブラックバスの冬のパターン
冬のバスは基本的に大半が水温が安定しているディープに集まっています。
水面付近は太陽光や風の影響で水温の変化が激しいため、バスの体力が奪われやすいからです。
なので、冬のバスは水温の安定したディープを起点にして、気候の良い日や、体力のある時に捕食のために条件のいいフィーディングポイントとなるエリアに上がってきます。
冬に条件のいいエリアは、太陽光を受けやすく、風を受けにくい場所や、温排水のあるエリアなどです。
冬のバスはあまり大きく動きたがらないので、このようなエリアがバスの集まるディープに隣接していると冬の一級ポイントとなります。
そして、水温が春に向けて徐々に上がってくると、冬に起点にしていたディープから次第に行動範囲を広げていき、春になるとスポーニングのからむシャローエリアにバスが入るようになってくるのです。
このようにしてバスの一年は巡っていきます。
▼冬のバス釣りの詳しい攻略法はこちら
バス釣り季節別の攻略法:まとめ
以上が、「ブラックバス季節の釣り方(シーズナルパターン)」バス釣り季節別の攻略法まとめとなります。
各季節の詳しいバスのパターンや釣り方は、それぞれ個別の記事に譲るとして、今回は重要なポイントを抽出してまとめてみました。
これで、ざっくりと一年のバスの流れが把握できたのではないかと思います。
この流れを理解した上で雑誌やweb上での情報を見てみると、一年の流れの中のどの状況のバスを釣っているのかをつかめるようになり、安易な情報に踊らされることなく、バス釣りへの理解がとても深まると思います。
また、もう一つ重要なポイントを付け加えておくと、ここで書いたのはバスのおおまかな一年の動きの流れであって、全てのバスがこのように一斉に動くわけではありません。
例えば、ある個体によっては、いち早く春にパターンに入るものもいれば、かなり遅れて春のパターンに入ってくるバスもいます。
つまり、フィールド内で違う季節のパターンのバスが混在する場合も多くあります。
このようなことも、実際に釣りをしていることで、「カレンダーの上ではもう完全に秋だけど、まだ夏を引きずっているバスが釣れた」など理解できてくるようになってきます。
このような発見もまた、バス釣りの楽しみのひとつです。