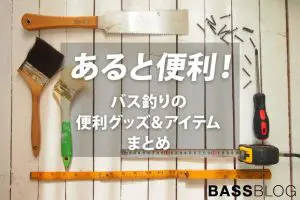今回は、「冬バスはなぜ釣れないのか?」についての解説と、釣れない冬バスを釣るコツについて書いてみました。
冬のバスは釣れないイメージがあります。
たしかに、水温が急激に下がり始める晩秋から初冬、とりわけ11月から12月にかけて、バスの活性は低くなることが多いです。
今回はこの、冬のブラックバスが釣れなくなる理由についても詳しく説明しようと思います。
逆説的ですが、この冬バスがなぜ釣れないのかを知れば、逆に釣れる冬バスを見つけやすくなり、冬でもバスを釣ることができるようになるはずです。
タップできる目次
冬のブラックバスが釣れない原因
冬のブラックバスが釣れなくなる原因は大きく分けて4つあります。
それでは、それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。
ターンオーバー
ターンオーバーについては、秋のバス釣りの記事で詳しく触れているので、参考にしてみてください。
ターンオーバーは、明らかにバスの活性を下げる要因となります。
ターンオーバーによる水質の悪化とその後の安定
意外と知られていないのは、実は、ターンオーバーは同じ場所で何度も起こることがあるということです。(水質の悪化と改善を繰り返す。)
一度急な冷え込みでターンオーバーが起きた後、水温が安定し、温かい陽が射し、風が吹かないなどの要因で水温が安定していくことがあります。
すると一時的ですが、このエリアのバスの活性が高まることがあります。
しかし、その安定した水も、その後にまた寒波が来たり北風が吹いたりすると、再度ターンオーバーで水質が悪化します。
すると再びバスの活性は急降下し、「釣れない」状況になってしまいます。
冬場に釣りやすい日を見極める
一概にターンオーバー=釣れないというわけではありません。
本当に悪いターンオーバーと、チャンスの見込めるターンオーバーがあります。
ここで重要なのは、「その日の天候だけで状況を判断しない」ということです。
ここ数日の気候がずっと安定していて温かく、風が少なければ、一度ターンオーバーが起きていても安定しつつある水なのでバスの活性は上がりつつあります。
逆に注意したいのは、釣りに行ったその一日だけが温かく、風もないような日です。
そんな釣り日和に思える日でも、前日までの気候が寒くて強風が吹き荒れていたのなら、おそらくターンオーバーが起きたばかりでバスの活性はかなり低くなっているはずです。
このような場合は、釣り人にとっては釣りやすい日でも、そのエリアでのバスの活性が低いので、釣るのはかなり難しくなります。
気温(水温)の急激な変化
人の場合でも、秋〜晩秋〜初冬〜真冬と、寒さが変化するのに合わせて、段階的に寒さのレベルを実感しているものです。
- 寒さのレベル1:晩秋
- 寒さのレベル2:初冬
- 寒さのレベル3:真冬
それぞれの冷え込みの段階ごとに、人間でもテンションが下がるように、冬のバスも冷え込み時に活性は下がっていきます。
気温が冷え込んだ直後のバスの活性は下がってしまいますが、冷え込みの後に気温がしばらく安定すれば、バスの活性は上がってきます。
そして、次の冷え込みが来るとまたバスの活性が下がり、またしばらく気温が安定するとバスの活性が上がる、というのを繰り返していきます。
冬の釣りは、冷え込み後の安定期が狙い目
このことからわかるのは、急な冷え込み後の気温の安定期が狙い目だということです。
冬の釣りは、特に連日の天気に注意しておくことが大切です。
気温の変動から、冷え込みのタイミングと、気温の安定期を見れば、バスの活性を予測することが出来きます。
冬バスはあまり腹をすかせていない
冬バスが釣れない原因には、冬バスはあまり腹をすかせていないということもあります。
その理由は、バスが秋に荒食いをして、冬の厳しい時期の備えて食いだめをしていることと、冬はあまり動かないのでエネルギーも消費しにくいということがあります。
これは、冬バスを釣ってみると、意外とガリガリではなく腹が膨れていることが結構多いことからもわかります。
冬バスの捕食は1〜2週間に1回
冬は水温が低いため、バスの身体の基礎代謝が下がり、消化速度が遅くなります。
具体的には、一度お腹いっぱいまで食べれば、1〜2週間は捕食しなくて良いらしいです。
これはどういうことかというと、夏の間は頻繁に捕食行動に出ていたバスも、冬になるとその頻度がかなり低くなってしまうということです。
なので、バスのフィーディング回数自体が減っているため、食欲のあるバスを食わせる釣りをしていると、なかなか出逢うのが難しい季節ということです。
だからこそ、食欲とは別のリアクションバイトのテクニックが大切になってくる季節ということです。
しかし、逆に言うと、頻度は下がっても確実にバスがフィーディングするタイミングはあり、そのタイミングにうまく合えば食わせの釣りも有効になるということでもあります。
リアクションバイトのテクニックについては、下の記事で詳しく書いているので、ぜひ参考にして欲しい。
釣り方(アプローチ)の変化の見逃し
冬のバスが釣れない原因として、釣りやすい秋の後の季節という落とし穴もあります。
おいしい「秋パターン」を引きずらないこと
秋は、バスの活性が高く釣りやすい季節のため、数もサイズも出やすく、比較的簡単に良い思いをすることができます。
しかし、そこから徐々にバスの活性が下がり、急な冷え込みがあり、と上記1〜3に書いたようなマイナス要因が続くことで、バスの状況が変わっていくため、本来であれば、アプローチ方法を変えていかないとバスは釣れません。
ところが人というものは良い思いにしがみつきたいもので、秋に釣れた「場所」と「ルアー」に執着してしまいます。
これが、この季節をより一層難しくしているところもあるでしょう。
冬に陥る「フィネス」という罠
また、バスが釣れなくなると、多くの人がより「フィネス」の方向に傾き、ルアーを小さくしようとします。
これは、夏の場合はとても有効ですが、実は冬の場合はあまり有効とは言えません。
その理由は、冬のバスは基本的に寒いのであまり動きたがらなため、小さなエサを細々と何度も動いて食べるよりも、大きなエサで一度で一気に済ませたいと思っているからです。
なので、ルアーのサイズも大きいほうが効くことが多いです。
ただ、動きはスロー寄りのほうが良いです。
モソモソ、モゾモゾと鈍い雰囲気を出すのが効果的で、冬バスにとっては、この時期のデカくてニブいエサは特にごちそうとなります。
参考価格:858円

冬バス「なぜ釣れないのか?」釣れない冬バスを釣るコツ!まとめ

以上が、冬バスはなぜ釣れないのか?という理由と、釣れない冬バスを釣るためのコツです。
晩秋から初冬にかけては、バスのコンディションに合わせて、今までの釣りと狙うポイントもアプローチの仕方もガラリと変わることが多いです。
前回来た時に釣れたから、同じ場所で同じルアーを投げるのではなくて、一度頭をリセットして、バスの状態をより理解し、気温や天気の変化を考慮した上で、そこからその日の釣りを組み立てていくことが大切です。
また、冬の釣りでは防寒対策が非常に大切となります。
寒さを忘れるほど快適に釣りに集中できれば、おのずと釣果も上がってくるものです。
釣りの防寒対策については、下の記事で詳しくまとめていますので、参考にしてみてください。
その他にも、防寒アイテムについてもまとめているので、ぜひ参考にして頂けたら幸いです。